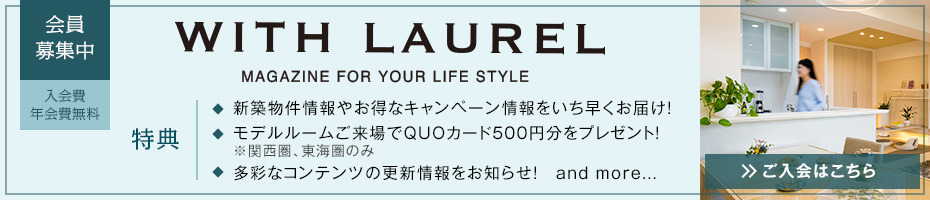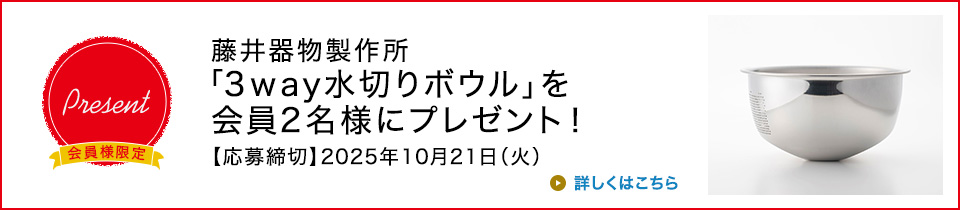2025.09.26 公開
誰もが心地よく暮らせる
住空間づくりのヒントを探って
永く快適に、安心して暮らし続けることができる住まいを追求する「ローレル」マンションシリーズ。商品企画担当の社員がさらなるアップデートをめざして、建築家の芦沢啓治さんに取材しました。多様化するライフスタイルや価値観の中で、これからの住まいの在り方についてお話をうかがいました。

Photo: Mario Depicolzuane
建築家 芦沢啓治さん
1996年横浜国立大学建築学科卒業。卒業後、建築家としてのキャリアをスタートし、super robotでの数年間にわたる家具制作を経て、2005年芦沢啓治建築設計事務所設立。11年東日本大震災の復旧をきっかけとし、地域市民がDIYできる石巻工房を創立。14年石巻工房を家具ブランドとして法人化。建築、インテリアだけにとどまらず、カリモク家具、KOKUYOといった家具ブランドとの協業など幅広い分野で活動。建築、インテリアから照明・家具デザインに一貫するフィロソフィー「正直なデザイン/Honest Design」によって生み出される作品は、国内外から高く評価されている。
建築家 芦沢啓治さんが掲げる“正直なデザイン”

Blue Bottle Coffee Shinsaibashi Cafe
Architect/Design: 芦沢啓治建築設計事務所
Photo: 見学友宙
— 建築・インテリアをはじめ、家具・照明のプロダクトデザインからブランディングなど多岐にわたって活躍されている芦沢さん。最近はどのようなお仕事が多いですか?
「僕たちがホスピタリティビジネスと呼んでいるホテルをはじめ、レストランやカフェが多いですね。ブルーボトルコーヒーの設計パートナーとして複数店舗を担当しており、最近だと2025年9月にオープンしたばかりの心斎橋カフェを手がけました。また、中国、台湾、シンガポール、ベトナムなどアジアを中心に海外の案件も多いですね」

dotcom coffee
Architect/Design: 芦沢啓治建築設計事務所
Photo: 見学友宙
— 芦沢さんは「正直なデザイン/Honest Design」をモットーに掲げられています。どんなことを大切にされているのですか?
「最近よく思うのは、人間中心の設計が大切だということ。たとえば街路樹って、歩く人がいるからこそ必要になるもので、人がいなければ要らない。つまり、人の存在が空間のデザインを決めるんです。こちらのビルを改装して事務所を移転した際に、1階をカフェにしたのも建築が主役ではなく、人に寄り添うことが大事だと考えたからです。目の前に公園があるので、1階に設計事務所があるよりも、住民に愛され、リラックスできるカフェがあるほうがいいですよね」

「僕たちの仕事は完成して終わりじゃなく、そこからどう使われるかが重要だと思います。お店の設計でも、『何時まで営業するのか』『昼と夜で雰囲気は変わるのか』といった使われ方を聞きます。誰が、どのように使うのか。その人たちへの深い共感がなければ、本当のデザインは生まれない。そこにいる人が幸せになれる空間をつくることが最も大切です」

「深い共感とは、相手が気づいていないニーズまで汲み取ることだと思います。レストランに行って、あなたの好きなものをつくると言われて、おいしいものが出てくるとは限らないですよね。やっぱり『おまかせ』というのは、料理人が積み重ねてきた味の極致みたいなところを食べるという贅沢さがあります。僕たちも『おまかせ』でちゃんとものがつくれる存在でありたいと思います」
本質的な居心地のよさを考える

— ライフスタイルや価値観が多様化する中で、フレキシブルに対応できるプランや商品を今後も検討していきたいと考えています。誰もが心地よく暮らせる住空間とは、どんなものでしょうか?
「あまりフレキシブルであることを難しく考えすぎなくてもいいと思うんです。気持ちいい空間って、やっぱり自然と人が集まるし、使いやすいものは誰にとっても使いやすい。僕らがつくるべきなのは、そういう本質的な居心地のよさだと思っています。たとえば、椅子のテキスタイルにウールを使って、触れると気持ちいいとか、無垢材に自然と手が伸びるような感触があるとか。そういう小さな感覚の積み重ねが大事なんです」

「レストランって、少し混んでいるくらいのほうが居心地がいいことってありますよね。それは、隣の会話がうっすら聞こえるような絶妙な距離感や音環境があるから。逆に静かすぎると、自分の声が響いて落ち着かない。だからこそ『音をどう扱うか』はすごく大事なんです。音に気を使っているレストランでは、机の下にスポンジを貼って会話しやすくしています。こうした繊細な配慮が、空間の体験価値をぐっと高めてくれるんです。実際に僕が手がけたカフェでも、アートを吸音材として使うなど、視覚と機能を両立させる工夫を施しました。こうした配慮を先に回り込んで考えられるかが、ホスピタリティデザインに求められていると思います」

— 繊細な配慮を積み重ねるために、日々どのようなインプットを行っているのですか?
「1年のうち3か月くらいは出張先のホテルで過ごしています。そこで感じた体験を、そのまま設計に活かすようにしています。実際に泊まる・食べる・触れることで得られる感覚は、図面や写真だけではわからない。だからこそ、この分野のデザインはやみつきになるほど面白いんです」
人間を中心にした住まいの設計

AZABU HILLS RESIDENCE
Architect/Design: 芦沢啓治建築設計事務所
Photo: 見学友宙
— つくり手が本質的な居心地のよさを見極め、しっかりと“おまかせ”を提案することが大事ということですね。芦沢さんが住宅をデザインする上で、「普遍的に変わらない大事な部分」と「ライフスタイルなどの変化によって対応していること」はありますか?
「人間のスケールって、昔から変わらないんです。僕らの体の大きさが同じだから、座りやすい椅子のサイズや、心地よい空間のプロポーションも基本的には変わらない。昔から美しいとされてきたものには、やっぱり理由があるんですよね。そうしたスケールやバランスが正しく整っていないと、美しく住むことも、美しく使うこともできないと思います」

A-S01 for Karimoku Case
Design:芦沢啓治
Photo: Jonas Bjerre-Poulsen
「よく僕はソファ問題と言っているんですが、床に座ってソファを背もたれ代わりにしているのをよく見かけます。畳やカーペットが消えて、僕たちは床から引き離された。でも、その名残として、みんなソファの前に座っているんですよね。だから僕は、ソファを“第2の床”としてデザインしています。小さい部屋だからといって小さいソファを置くと、あぐらもかけないし、寝ることもできない。体に合った奥行きとサイズを確保することが、心地よい空間の鍵なんです」

「姿勢が悪くなりがちな椅子も多い中で、僕がデザインしたこの椅子は、背筋が自然と立つような設計にしています。わずかな角度の違いが、大きな差を生むんですよ。些細な違和感を見逃さずに、座り心地と姿勢の良さを両立させるのが大事です。僕らの行動って、実は道具によって大きく制限されています。だからこそ、家具の精度が生活の質に直結するんです」

Blue Bottle Coffee Shibuya Cafe
Architect: 芦沢啓治建築設計事務所
Photo: Ben Richard
「また、まぶしさはストレスになります。脳が余計なエネルギーを使うので、集中できない。だから、照明の設計もとても重要です。直接光源を見なくていいようにルーバーで目線を遮ったり、天井を明るく反射させたり、天井に光がやわらかく広がるよう照明自体のデザインを工夫することで、空間の印象が変わるんです。こうした丁寧な積み重ねが、居心地の良さにつながります」

— 芦沢さんの作品は華美さではなく、過ごす人の豊かさに寄り添った空間だと感じるのですが、どのような想いでデザインされているのでしょうか?
「高級に見せようとしすぎて居心地が悪くなってしまうこともあります。見た瞬間から素材同士がけんかしているように感じる空間もありますよね。そこで僕らは、あえて“ダウングレード”することもあります。グレードを落として、居心地を上げる方向に持っていくんです。最近は高級感に飽きてきている人も多いと思います。僕らが日々の生活の中で感じている『いい体験』や『いい気持ち』を活かしたほうがいい。これまで見過ごされてきた体験価値に少し重心を置くだけで、それに気づく人はいると思います」

コペンハーゲンの街並み
— 住宅では昔のように家族みんなが居間に集まるより、個々で過ごす時間が増えていると感じています。リビングよりも各居室を広くするべきか、それでは家族で過ごす時間が失われるのでは…とそのバランスに悩むのですが、芦沢さんはどのようにお考えでしょうか?
「理想をどう持つかですよね。最近、デンマークのコペンハーゲンに行ってきたんですけど、あそこはまさに人間中心主義の都市でした。ほとんどの人が自転車で移動していて、駐車場を気にせずカフェにも気軽に立ち寄れたり、公園や水辺もしっかりと整備されていて、人は自然と外に出て公共空間を使っています」

「そうやって公共の場で人と人がつながることで、『人は信用できる』と思える社会が生まれる。それって、家の中の設計にもつながる考え方だと思うんです。みんなやっぱり一人じゃ生きていけないし、自分さえよければそれが本当に住みやすい環境なのか、疑問は残ります。時代に迎合するだけではなく、『家族ってどう在るべきか』『どういう社会が理想なのか』という問いから離れてはいけないと思うんです。住宅という社会インフラをつくるなかで、自分たちが思い描く美しい未来に対して動いてもらいたいなと思います」
多様化するライフスタイルや価値観の中でも、誰もが体感できる普遍的な居心地のよさ。それは、つくり手自身が日々の暮らしで体験した心地よさを大事にしながら、理想の暮らしを思い描き、細やかな配慮の積み重ねで生まれるものだと、商品企画担当者も改めて実感できたようです。