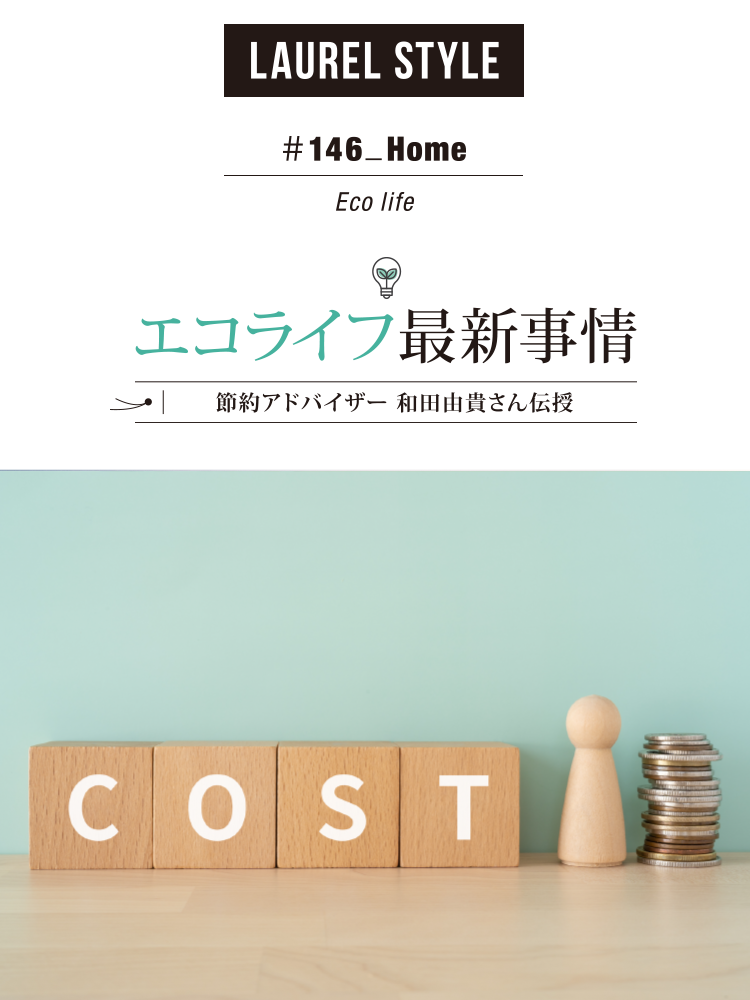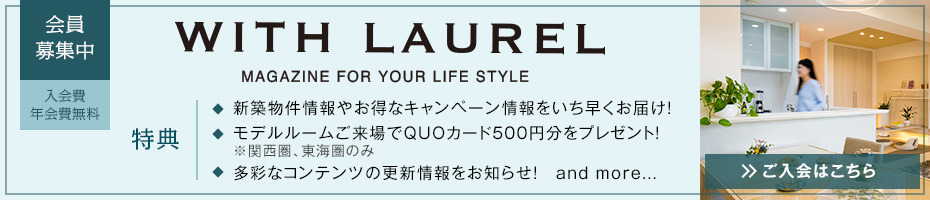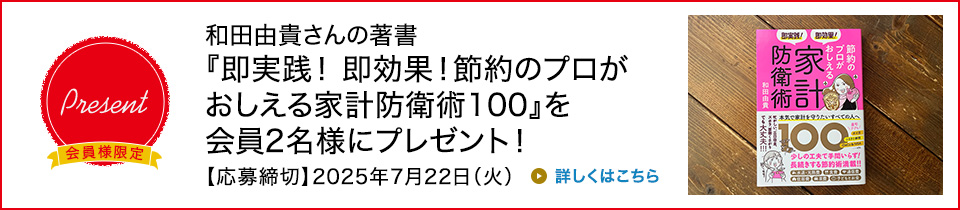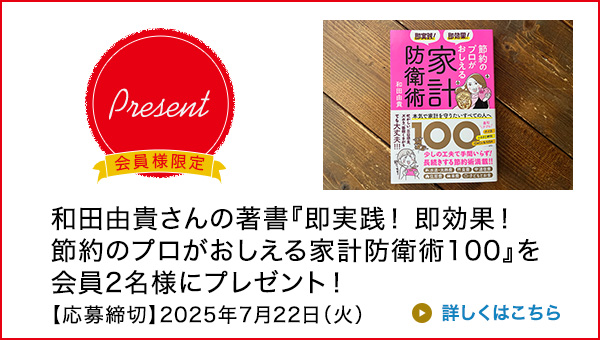2025.06.20 公開
Eco life
できるだけストレスのない節約術を
高騰する物価や光熱費と家計が厳しくなる今、できるだけストレスのない節約術を知りたいところ。そこで、今回は「節約は、無理をしないで楽しく!」をモットーに掲げる節約アドバイザー 和田由貴さんに取材し、長続きする節約術や光熱費・食費対策などを教えていただきました。
ムリせず楽しく、長続きする節約術

自分にとって大切なものを考える
— 節約=ガマンするというイメージを持ってしまいがちですが、ムリなく節約し続けられるための大事なポイントとは?
「まずは、自分にとって大切なものを考えてみましょう。何にお金を使いたいのかを明確にすれば、自ずと削れる部分も見えてきます。例えば、『年に1回は海外旅行に行きたい』のであれば、それ以外のなんとなくの出費を抑えれば、やりたいことをガマンせず、節約も叶えられる。こうした“メリハリのあるお金の使い方”が大事ですね」

買い物は安いからではなく必要なものを
—なんとなくの出費で特に注意したいことは?
「私たちはいろいろな理由で買い物をしますよね。安い・期間限定・ポイントが付くなど。でも、本当に大事なのは“自分が本当に必要としているか”です。買う前に一度、立ち止まって考える冷却期間を設けてみましょう。冷静になって考えれば、『 他に必要なものはない?』『もっと良いものがあるかも』『他なら安く買えるかも』と、前向きな代替案が思いつくかもしれません。
『買ったからにはしっかり使い切る』という視点も大切です。セールで服を買ったとしても、実際に全然着なければお得ではありませんよね。逆に定価で買った服でも、必要だから買ったものは着る回数も多くなって、1回あたりのコストは安く済むことも。つまり、費用対効果で考えることが重要だと思います」

使途不明金は要注意。ざっくりでも支出を把握
「収入や支出が把握できていれば、『今これは買っても大丈夫』とか『今月は使いすぎているからやめておこう』と判断しやすくなります。逆に、なんとなくの出費=使途不明金が多い人は注意が必要です。家計簿を細かくつける必要はありませんが、『何にいくら使ったか』がわからない状態を放置するのは良くないですね。
支出の記録が残るように、電子マネーやクレジットカードなど利用履歴が確認できる手段で買い物をするようにして、後から見直せるようにしておくことをおすすめします。
節約が長続きするコツは、ルールを決めて実行すること。でも、厳しすぎて守れないルールを決めても長続きしませんから、まずは簡単にできることから始めましょう。家計簿もムリなく続けられるよう、あまり細かくせず、おおまかに収支がわかればOKです」

上手に貯めて活かしたい「ポイント」
「スマホのキャリアやキャッシュレス決済などに連動した『ポイント』を上手に貯めて、使えば節約につながります。異なるポイントを並行して貯めるよりも、的を絞ったほうがより貯まりやすくなります。楽天ポイントやdポイント、Pontaポイント、PayPayポイントといった、ご自身が使っているスマホのキャリアごとに合わせたり、利用しやすいポイントに的を絞ってみましょう。本来、必要なものを買ってポイントがつけばお得ですが、ポイントのために無駄なものを買ってしまうのは逆効果。また、ポイントを使うときも『ポイント=お金』として使う意識が必要です。『もらったものだから』と無駄遣いしてしまうと節約効果がなくなってしまいます」
水道・光熱費をムダなくムリせず節約

給湯
「家庭で使うエネルギーの約3割を占めているのが給湯です。エアコンなどの家電とは違って目に見えにくいので、意外と盲点になりがちですが、常温の水とお湯とでは、コストが3倍以上変わります。給湯パネルのスイッチがオンのままだと、ちょっとお湯を出しただけでもガス代がかかってしまいます。特に、シングルレバー水栓などで真ん中にレバーがあると、自分は水を使ってるつもりでも、少しお湯が混ざって無駄なコストが発生してしまうので、注意が必要です。入浴中にシャワーを出しっぱなしにするのも控えたいですね」

冷暖房
「まず大切なのが、冷暖房を効率よく効かせるための環境を整えること。冷気や暖気が部屋の外に流出しないよう窓の対策が重要です。夏はできるだけ窓の外側で日射を遮り、冬はカーテンなどで内側から遮熱します。また、設定温度を1℃変えるだけでおよそ10%以上の電気代を節約できます。夏は扇風機も使って体感温度を下げたり、冬はサーキュレーターを使って暖気を循環させたり、これらを併用しながら設定温度を調整すれば節電効果も期待できます」

冷蔵庫
「省エネ性能が低い古い機種を使っていると、どんなに気をつけても節約効果は限定的。冷蔵庫は壊れるまで使いがちですが、突然壊れるリスクがあり、最近は在庫不足で納品まで時間がかかるケースもあります。冷蔵庫の平均使用年数は約14年といわれており、それを大幅に超えているようなら、買い替えも検討したいところです。また、使い方として注意したいのが、物を詰め込みすぎないこと。冷気の吹き出し口を物で塞いでしまうと、効率が悪くなり電気代が余計にかかります。冷気が庫内を循環できるように、隙間を確保しましょう」

照明
「照明はこまめに消すのが基本ですね。今はLEDが主流ですが、LEDの普及率は6割ほどといわれています。白熱電球はLEDに比べて6〜10倍、蛍光灯は約2倍、電気代がかかってしまうため、LEDへの交換がおすすめです。点灯回数による劣化もほとんどなく、玄関やトイレなど、短時間しか使わない場所は人感センサー付きのLEDに変えてみては。また、お部屋で発熱量の多い蛍光灯や白熱灯を使っていると、それ自体が部屋を暑くし、冷房効率が悪くなることも」

テレビ
「テレビをなんとなくつけっぱなしにしていると電気代がもったいないですよね。音が欲しいだけならラジオや音楽配信サービスに切り替えてみてはいかがでしょう。また、テレビの画面設定も注意が必要です。輝度が高く設定されていると画面が明るい分、電気代も増えてしまいます。最近は、画面の明るさを自動調整してくれる機種が多いので、画面設定を確認してみましょう。また、テレビを買い替える際に気をつけたいのが有機ELテレビです。鮮やかな映像が魅力的ですが、消費電力量は液晶テレビの1.5倍ほどになることもあるため要注意です」

洗濯・乾燥
「浴室乾燥機やヒーター式の乾燥機は、電気代がかかるため、乾燥機を多用する方は注意が必要です。可能であれば、天日干しが一番コストがかからない方法です。外に干せない場合でも、扇風機や除湿機を併用して乾燥時間を短縮することで、電気代を抑えることができます。また、タオルのサイズも見直したいポイントです。バスタオルをスポーツタオルサイズにすれば、干すスペースも取らず、乾きやすいので節約につながります」

知らないことで損をする!?「通信費」
「家計の中には、住居費や水道光熱費、通信費、保険料などさまざまな固定費があります。この固定費を見直せば節約効果が大きいのですが、大きな壁が立ちはだかります。それは『思い込み』と『面倒』と感じること。例えば、携帯電話の契約を格安スマホや格安SIMを提供しているMVNOに乗り換えれば、通信費が大きく節約できる場合があります。でも、『家族で同じキャリアを使っているから今のままが安いはず』『なんとなく面倒だから』と動かない人が意外と多いんです。知らないと損をすることもあるので、まずは興味を持って調べてみませんか」
食費をムダなくムリせず節約

安く買うより余らせない
「今すぐ必要ないものでも『安いから』という理由で買いだめてしまうと、結果的に無駄になってしまうことが多いですね。安く買えたことで、節約できたと錯覚しがちですが、本当に大切なのは無駄を出さないこと。大量に買って使い切れずに捨てるのはもちろんNGですが、『とにかく消費しなきゃ』と無理やり使い切るのもまた無駄ですよね。節約は安く買うより余らせないが大事です。また、嗜好品も要注意。お菓子やお酒など家にストックがたくさんあるとつい消費量が増えてしまいます」

献立を考えて買い物=節約になりにくい
「事前に献立を考えてから買い物に行くと、必要な食材が高くても無理して買わざるを得なくなったり、買った食材を使い切れずに余らせたり…。計画的に見えても節約とは程遠いことになってしまいます。それなら、その日の特売品を見て、冷蔵庫に残った食材と合わせて献立を考えられるとムダもなくなります。理想は、家の中に残っている食材を使い切ることを最優先に考えて、買い物に行くこと。限られた食材で臨機応変にメニューを考えられると、フードロスを減らし、食費の節約もうまくいきますよ」

日用品のストックもマイルールを
「日用品も同じで、たくさんあると気が緩んでしまい、使い方が雑になりがち。だからこそ『必要な分だけ、管理できる範囲で持つ』というのが理想ですね。私は調味料や洗剤などのストックは、1つだけ持つというルールを決めています。今使っているものが空になって新しいものを開けたら、買い物リストに入れて、1ヶ月分まとめて購入するようにしています。こうしてルール化しておけば、『ストックもないから仕方なく定価で買う』といったことが防げ、買い物の手間も減らせます」

知らないことで損をする!?「新しい制度」
「最近は、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)といった制度がありますが、仕組みがよくわからず、敬遠されがちですね。『聞いたことはあるけど内容は知らない』という人が多いと思います。でも、これらの制度は知るだけで大きな得につながる可能性があります。
例えば、 iDeCoは節税効果がとても大きいのがポイントです。月々の掛金を拠出して運用し、60歳以降に受取が可能に。掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税、年金や一時金として受け取るときも税金の控除があります。こうした新しい制度やサービスは次々出てくるので、アンテナを張って、『なんとなくこういう仕組みなんだ』というレベルでも知っておくことが大事ですね」